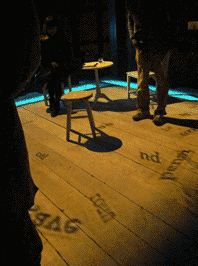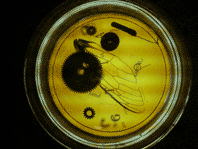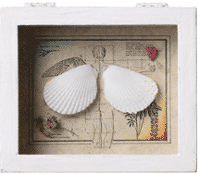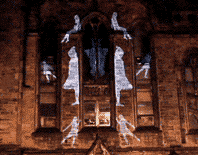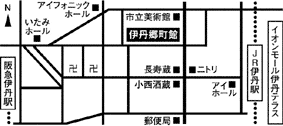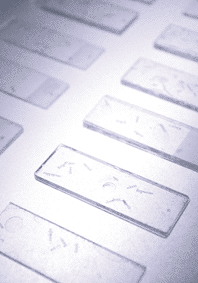 |
現存する最古の酒蔵での展覧会 |
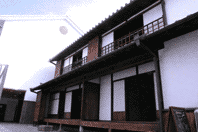  |
【会場となる伊丹市立伊丹郷町館とは】 |
『CONSIDERATION/考察:その一』 ナマエとは何でしょう? ナマエによって物は固定され認識される。確かにナマエがあれば便利です。物事を伝えやすい。でも本当にそうでしょうか? ナマエによって固定された情報からこぼれ落ちたたくさんのイメージが、僕にはあるように思えます。そのこぼれたモノの方が実は重要だったりする。grafの服部さんとのトークセッション「地図のない話」でいつも浮かび上がってくる言葉に「無駄」「遠回り」「不便さ」があります。これらはかなり重要なキーワードなのではないかと、僕らは思っています。 何かを説明するときにナマエでは無くその周りにある情報を出来るだけ伝える。出来る事なら現物を見せる。面倒で時間がかかる作業ですが、その無駄とも思える七転八倒のなかから伝わってくる何かが存在するように、僕には思えます。ナマエのないあやふやなカタチ。固定されていないそのカタチを僕らは必死で捕まえようとしています。それをたった一言のナマエで片付けてほしくない。大切な事には足を運び、自分の身体で感じ、考える。単なる情報ではなく、そのモノをちゃんとイメージするために。 この作品展がそのヒントになれば良いと思っています。 |
|
『CONSIDERATION
/考察:その二』 酒蔵で作品展をするという事。酒造りで有名な伊丹で展覧会をする。僕がすぐに考えたのは菌の事でした。菌による醗酵と化学反応。気温や湿度の変化。その場所が持っている特徴や空気が、米や水と同じように重要だと聞いた事があります。そして時間。すべてカタチのないモノたち、変化し続けるモノたちです。僕の作品のコンセプトと重なったこれらのキーワードから「ナマエのないカタチ」は生まれました。 そして、僕の作品にはナマエがありません。 「この作品のタイトルは何ですか?」とよく聞かれることがあります。そのたびに僕は「砂粒ひとつひとつにナマエが無いように、個々の作品にはナマエが無いのです。たとえばサハラ砂漠やゴビ砂漠のように砂漠のナマエはあっても、そこの砂ひと粒ひと粒にはナマエは無い。あなたもあなたのナマエはあるけれど、あなたを形作っている細胞のひとつひとつにはナマエが無いのと同じです。」と答えています。ですから僕の作品にはsandscapeというプロジェクトの名称と展覧会ごとのタイトルがあるだけで、個々の作品にはナマエがありません。これらの作品は細胞や砂粒と同じように展覧会ごとに組み合わせを変え、細胞分裂のように、砂漠の風紋のように見え方を変えていくのです。僕が展覧会や作品集のタイトルに使っているoperationには、作業や働き・影響や効果・手術・作戦計画といった意味と、オペラの語源になった作品という意味があります。僕がこの言葉を使うのは展覧会会場や作品集自体を、ひとつの作品ととらえている事と、sandscape(砂の風景)へと向かう作業や効果ととらえているいる事の、二つの理由からです。 砂は、違う場所に飛んでゆけば、そこの砂漠のナマエになる。固まれば石や岩になります。あなたから引き継がれた細胞は、また違う別のナマエの誰かになり、引き継がれなかった細胞もまた別のナニカになっていく。そうやって外側のカタチやナマエを変えながら、永遠とつながっていくモノ達。sandscapeとはそうした変化の物語なのです。 |
|
『PROFILE-コレマデのカタチ』 ◆黒田武志 Kuroda Takeshi (sandscape) 1962年岡山県出身。造形作家・グラフィックデザイナー。sandscape主宰。大阪を中心にインスタレーション、オブジェ等の作品を発表。桐野夏生・島田荘司・長野まゆみなど小説の表紙や挿画に作品が使用される。2001年美術館巡回展『BoxArtム箱の中の秘められた宝物たちム』で世界のBOXARTアーティスト32人の中に選ばれる。また、雑誌・単行本のアートディレクターション・ロゴタイプ等、グラフィックデザイナーとしても活躍。演劇との接点も多く、数々の劇団のフライヤーやパンフレットを手掛けている。HEP HALLプロデュース『ハムレット』(2004)『夏の夜の夢』(2005)では舞台美術から衣裳・小道具・宣伝美術まで、全体の世界観をまとめるアートディレクションを担当。「維新派」では『キートン』(2004)『ナツノトビラ』(2005)『nostalgia』(2007)『台湾の灰色の牛が背のびをしたとき』(2010)の舞台美術を担当。2008年2月の大規模個展『百年後の博物館』(HEP HALL)では4500人を動員、タテタカコ、SIBERIAN NEWSPAPERらと音楽とアートのコラボを実現した。2008年8月〜2010年1月は18ヶ月間毎月新作を発表する連続プロジェクト「新作実験室[6×3ュ18]」(bar FINNEGANS WAKE1+1)を行う。オブジェ作品集に『ON THE PAPER』『不純物100%』がある。 http://homepage.mac.com/sandscape/ ◆服部滋樹 Hattori Shigeki (graf) 1970年大阪生まれ。graf代表・デザイナー・クリエイティブディレクター 京都精華大学デザイン学部建築学科 准教授 1998年大阪、南堀江にショールーム“graf”をオープン。2000年“decorative mode no.3”設立。同年、中之島に移転し、“graf bld.”を設立。オリジナル家具の企画・製作・販売、店舗・住宅・建築設計、グラフィックデザイン、アートディレクション、ブランディングに至るまでプロジェクトごとに幅広い活動を行っている。2005年 咲くやこの花賞 美術部門 受賞。 2006年 第三回アサヒビール芸術賞 受賞。 graf:decorativemode no.3 design inc. スペースデザイン、家具、照明、グラフィック、プロダクトデザイン、アートから食に至るまで「暮らしのための構造」を考えてものづくりをするクリエイティブユニット。既存のものにとらわれない自由なデザイン展開で、多方面にわたり活動中。 http://www.graf-d3.com ◆mama!milk 生駒祐子(アコーディオン)、清水恒輔(コントラバス)を軸とするユニット。 京都を拠点に、各地の様々な空間で演奏を重ね、その独創性溢れる数々のアルバム作品と、「Cinematic Beauty」とも評される艶やかなパフォーマンスが、インストゥルメンタル音楽の世界で独自の輝きを放っている。近年は、アナログ・レコーディングによる「Fragrance of Notes」、ホール録音による「Parade」、とある廃墟でのフィールド・レコーディングによる「Quietude」という、それぞれ独特 の美に彩られたアルバム作品を発表。同時に、アコーディオンとコントラバスのシンプルなデュオから、ゲストを迎えてのコンボやアンサンブルなど、様々なスタイルで演奏を行う他、映画や舞台音楽など、多岐にわたる魅惑的な活動を自在に展開している。 http://www.mamamilk.net ◆吉光清隆 Yoshimitsu Kiyotaka 1978年生。映像作家。インスタレーションや舞台作品、パフォーマンスなど空間を意識した映像作品を制作している。演劇、ダンス、現代美術など様々なアーティストに対しての映像提供、協力も多数。建築物の形を利用した映像を投影する「Architecture Projection」プロジェクト等を展開中。ソロ作品に「layer」神戸ビエンナーレ2007、「colors」BIWAKOビエンナーレ2010、等がある。また、言葉を使用しないパフォーマンスグループ「the original tempo」のメンバーとしてシンガポール・韓国・ロンドン・スコットランド等での公演を行う。デザイン事務所cursorとのユニットで、生活の中にあるものを今までと違う感覚でデザインする「mono×life×projection」としても活動中。 youtube |
|
|
■会場 |
|
主催■伊丹市立伊丹郷町館[伊丹市+公益財団法人 伊丹市文化振興財団] |
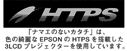 |